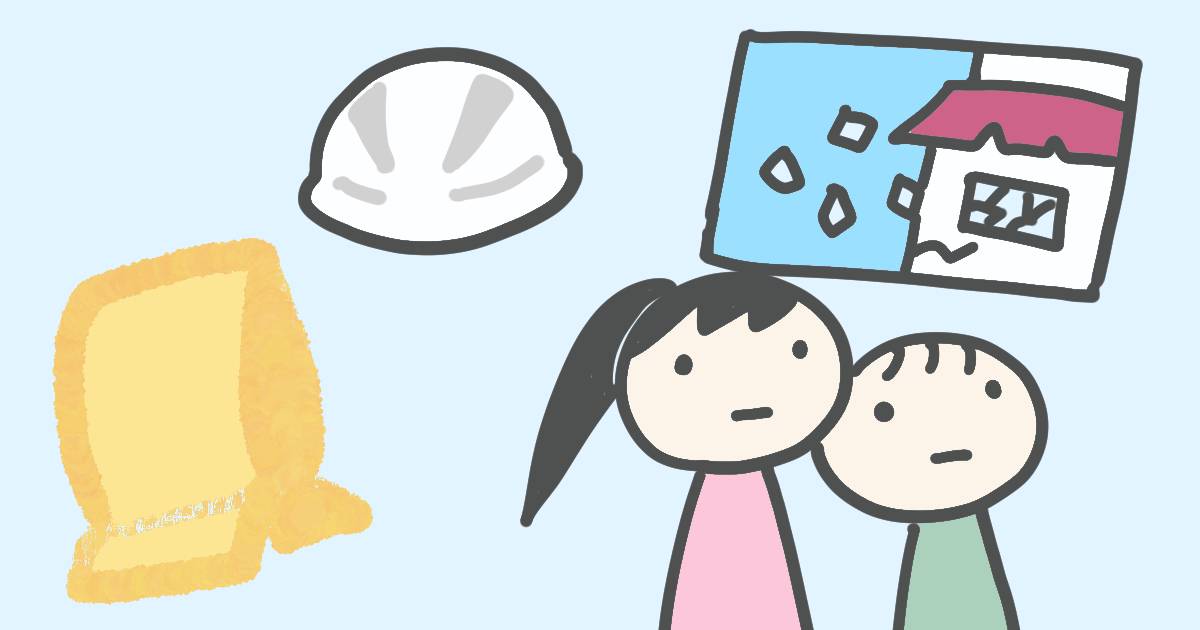保育園でも毎月ある避難訓練。火事や地震などをを想定して毎月行われています。
0・1歳の子ども達は、先生の側で一緒に待つ・避難をする…という事に慣れていきます。自力での避難は難しいので、多くは抱っこ紐や避難用(お散歩)カートで避難をします。抱っこにおんぶはなかなか大変でしたね。(汗)
2歳になると手をつないで歩けるようになり、先生の指示を聞いて避難もしますが、突然の放送や避難にビックリして泣いてしまう子も出てきます。「ダンゴムシになるよ~」と時々遊びながら身を守る姿勢を教えたり、防災クッションをかぶってみたりと少しずつ避難訓練の話に触れていきます。
3歳以上になると、「危ないから逃げる」という意味が少しずつ理解できるようになってくるので、避難もスムーズになってきます。
紙芝居や動画で分かりやすく知ることもできますが、やはり実際に自分で動いて学ぶのは重要です。
まだしっかりと理解ができなくても、避難経路や避難場所を確認する・命を守るための判断力を鍛えることもできます。
「子ども達は大人がしっかり引っ張らねば!」と思っていましたが、全員が揃っている時ではなく自由遊びの時間に地震の避難訓練がスタート。
「AちゃんとBちゃん(年中組)が部屋にいない!お遊戯室へ行くって言ってたっけ!」
先生達で手分けをして、集まった子の避難誘導や、その場にいない子の探索に動きました。
遊戯室には先生がいなかったのでオロオロしていいるかも…と駆けつけてみると、予想に反してしっかり身を守る態勢が取れていました。しかも「地震時には窓から離れるように」という点も守っていたのですごい!
 チイコ
チイコちゃんと自分たちで考えて対応ができてえらーーい
訓練日ではないけれど…
壁をドンドン叩いてにぎやかに遊んでいた1歳児クラスの子ども達。
用事があって隣の2歳児クラスに向かった先生が見たのは、先生も子どもも皆テーブルの下に避難している状況…。
私「えッ!??避難訓練の放送入りました??」
2歳担任「なんかすごい音が響いていたよ??(リアルに)地震でしょ?」
………すみません!!その音1歳児クラス(うち)です~~~~!!(涙)



ぉぉお騒がせしましたぁ。



2歳児さん、冷静に机の下でじっとしてたんだ…。
火事の避難訓練が始まった時、放送を聞いた年少組のC君が「ハンカチあるよ!マスクする!!」とハンカチを準備。ちゃんと放送も聞いているね。
感染症が流行りだしてからマスクを着けることが多くはなりましたが、煙を吸わないようにハンカチを使うということを知っておくことは大事ですね。
初めての避難訓練では慌ててしまう事ももちろんあります。
「上履きのままでいいから外へ出て。」と指示を出す先生。外へ行くには靴を履き替えるというのが当たり前だった子は、慌てて履き替えようとしたり「???」戸惑うことも…。
園生活が始まったばかりの4・5月には、そのまま帰るのだと思ったようで、カバンと水筒まで準備しようとする子もいたっけ…。
とにかく避難第一!
1歳児クラス。先生達であらかじめどの子を連れて行くのか相談もします。歩けない子はおんぶ・抱っこ。歩ける子はお散歩カートに乗せて移動など…。
避難訓練のスケジュールがだいたい分かっていると、ついつい先におんぶ紐やヘルメットを取りやすい場所に準備してしまうんです。(汗)いきなり来るものに対しての訓練なんだから「それじゃぁ訓練にならないー!」とツッコミをもらいそうですが。
(その直後↓)
園長先生「みんな遊びにきたよー❀あれ??先生達なんか準備万端過ぎん?!」
………お部屋に遊びに来た園長先生に見つかって指摘されました。(汗)すみません(涙)。



待ち構え過ぎだ。
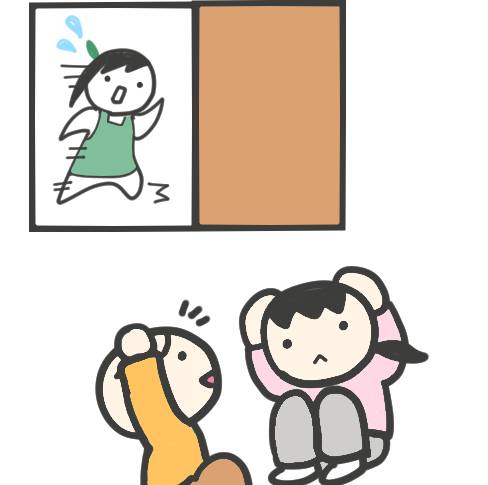
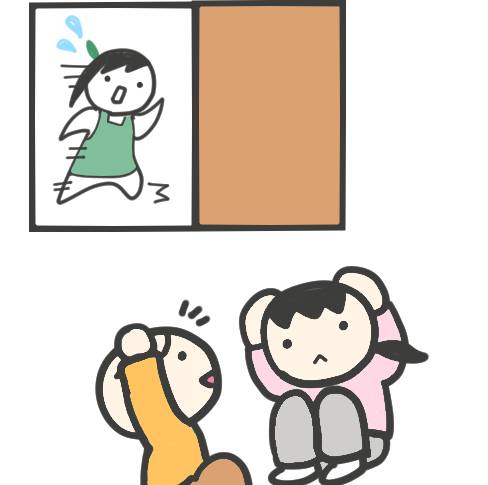




たくさん避難訓練をやってきて、子ども達もそうですが先生(大人)も落ち着いて動くことがきるのでやっぱり訓練は大事だな、と感じました。
また、食べるものについても給食でアルファ米を食べる機会が設けられていたのでいただいたのですが、ある味のご飯はすごく不評で全然食べれない事もありました。普段普通に食べているご飯も、災害時には非常食になることも考えると、非常食もたまに食べてみることも大事なんだろうと思いました。